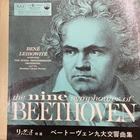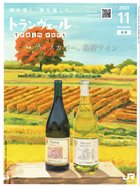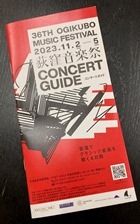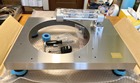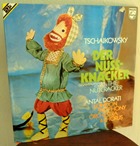店主日誌カテゴリ
商品カテゴリ一覧
- アナログ・プレーヤー
- フォノ・カートリッジ
- トーンアーム&関連製品
- フォノ・ステージ&MCトランス
- ヘッドシェル&関連用品
- アナログ・プレーヤー用品
- アナログ・プレーヤー調整&メンテナンス用品
- オーダーメイド・ダストカバー
- レコードケア用品
- レコード内袋,カバーなど
- プレーヤー&カートリッジ修理
- 真空管アンプ
- 真空管
- スピーカー・システム
- スーパートゥイーター
- スピーカー・ユニット
- CD/SACDプレーヤー&トランスポート
- D/Aコンバーター
- インテグレーテッド・アンプ
- パワーアンプ
- プリアンプ
- インシュレーター,スパイク&プラットフォーム
- ケーブル&関連製品
- ヘッドフォン
- オーディオ・ラック
- スピーカー・スタンド
- ケミカルズ
- その他、アクセサリー
- パーツ、材料
- ツール
- レコード&オーディオ雑貨
- SPECIAL OFFER !
- PRE-OWNED(中古アイテム)
- 中古オーディオ買い取り
- 中古レコード買取り
- アナログ・レコード
- 貴重ライヴCD/PREMIEREレーベル
- 幻のSP, LP復刻CD/ SAKURAPHON レーベル
- 中古CD
- 書籍
ショッピングカート
カートの中身
カートは空です。
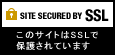
|
ホーム |
店主日誌
店主日誌
記事検索
店主日誌:190件
年末恒例の第9
スピードメーター、交換
スマート水道メーター
アナログ・プレーヤーの調整
パラダイム Persona B、ご納品
新幹線常備誌『トランヴェール』で当店を紹介頂きました
荻窪音楽祭 2023
雑誌取材
ウエスギ U-BROS-300AH ご納品
パラダイム Persona B ご納品
Technics SP-10R用 SAECターンテーブルデッキ、Clearaudio TT3 リニアトラッキングアーム
パラダイム Persona B ご納品
JBL 4309 ご納品
ウィーンアコースティクス・スピーカー、ご納品
Reed 1C プレーヤーご納品
CECのD/Aコンバーター新製品
300Bを換えるとどうか?
ICチップ受難
プライベート・ニューイヤーコンサート
年末の2枚
|